ここから本文です。
労働争議の調整
労働争議の調整とは、労働委員会が労働者の団体(労働組合、争議団)と使用者との間に起きた紛争について、解決の糸口を見いだすための手助けを行うものです。
1.調整の対象となる事項
2.調整の手続き
3.あっせんの手続き
4.Q&A(個人の労働者向け)、(使用者向け)
5.申請の方法
6.調整事件の取扱状況
7.労働争議(あっせん)の事例
1.調整の対象となる事項
次のような事項が対象となります。
- 労働組合に関する事項(組合活動、組合承認など)
- 労働協約に関する事項(労働協約の締結・改定・解釈・実施など)
- 労働条件に関する事項(賃金、退職金、諸手当、労働時間、定年制など)
- 経営・人事に関する事項(事業の休止・廃止、事業縮小、操業短縮、一時帰休、企業合併、営業譲渡、人事考課、昇格、休職など、労働条件に関するものに限られる)
- 福利厚生に関する事項
- 団体交渉の促進に関する事項
争議の実状が調整に適さないと認められる場合は、調整を行わないこともありますので、調整の対象になるかどうか疑問がありましたら、申請書を提出する前に、事務局に相談してください。

2.調整の手続き
労働委員会が行う労働争議の調整には、1あっせん、2調停、3仲裁の三種類があります。
どの方法によって調整を行うかについては、当事者が選択します。このうち、あっせんの方法が最も多く利用されています。
これらの調整の方法の相違点は、概ね次のとおりです。
| 区分 | あっせん | 調停 | 仲裁 |
|---|---|---|---|
| 調整の主体 | あっせん員:当労働委員会では、通例、公益委員・労働者委員・使用者委員各1名ずつの3名が指名されます。 | 調停委員会:当労働委員会では、通例、公益委員・労働者委員・使用者委員各1名ずつの3名の調停委員から構成されます。 | 仲裁委員会:当労働委員会では、通例、公益委員3名又は5名の仲裁委員から構成されます。 |
| 開始要件 |
|
|
|
| 調整の機能・効果 |
|
|
|
労働関係調整法による調整をする場合に、労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、使用者がその労働者を解雇したりその他不利益な取扱いをすることは、不当労働行為として労働組合法第7条第4号によって禁止されています。
3.あっせんの手続き
最も多く利用されているあっせんの手続きについて、御紹介します。
あっせんは、あっせん員候補者の中から労働委員会の会長によって指名されたあっせん員が、当事者の仲立ちをして双方の主張の要点を確かめ、対立点を明らかにしながら、当事者間の話し合いを取り持ち、あるいは主張を取りなすことにより、争議の解決を図る手続きです。
なお、あっせん員候補者は、労働委員会委員を含め、労働争議の解決に援助を与えることができる学識経験者の中から、あらかじめ労働委員会が委嘱しています。
当労働委員会では、公益委員、労働者委員、使用者委員からそれぞれ1名のあっせん員が指名され、三者構成のあっせん員が手続きに参加します。
あっせんの手続き
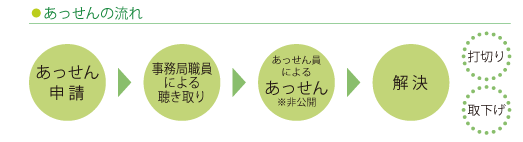
両当事者の主張が折り合わないときなどは、あっせんが打ち切られることがあります。
当事者同士の話合いで問題が解決したなど、あっせんの必要がなくなったときは、申請者はいつでもあっせんを取り下げることができます。
4.Q&A(個人の労働者向け)、(使用者向け)
5.申請の方法
以下の方法により申請できます。
※ 宮城県労働委員会事務局では労働争議の調整に関するご相談を承っております。手続きに関することなど、申請前にご相談いただくことをお勧めします。
(相談先: 宮城県労働委員会事務局審査調整課調整班 022-211-3787)
| 手続き種別 | 方法 |
|---|---|
| 書面による申請 | 書面による申請を行う場合、申請書様式をダウンロードの上、来庁等により、申請書等を当委員会にご提出ください。 |
| 電子申請システムによる申請 |
≪電子申請システムを用いた申請の流れ≫ (1)認証IDの付与申請 誤った手続やなりすましによる手続を防ぐため、電子申請システムを利用して労働争議の調整に関する申請を行う場合は、当委員会が発行する「認証ID」を利用いただく必要がありますので、電子申請システムにおいて、以下のフォームから認証IDの付与申請をしてください。 ※認証IDの付与申請を行う前に、お電話によりご連絡ください。 労働争議の調整の申請に係る認証ID付与の申請(外部サイトへリンク) (2)当委員会からの認証IDの連絡 当委員会から、認証IDをメールにより連絡します。 (3)電子申請 認証IDを利用し、以下のフォームから申請をしてください。 |
6.調整事件の取扱状況
7.労働争議(あっせん)の事例
以下の事例は、宮城県労働委員会で実際に取り扱った労働争議(あっせん)の事例をもとに、個人のプライバシー等に配慮して多少内容を変更しています。
労働争議のご理解のための参考としてください。
事例(組合が団体交渉のルールの明確化を求めた事例)
労働組合Xと食品加工業を営む株式会社Yとの間で、夏季の賞与の額を議題とする団体交渉が行われていました。
2回目の団体交渉が終了した際、まだ、妥結にはいたっていませんでしたが、会社は組合に対して、「団体交渉において、会社が提示した金額を各従業員の口座に振り込む。」と通知しました。
組合員の間では、「妥結をしていないにも関わらず、賞与を一方的に振り込むことは許されない。」との声が上がりました。
また、過去にも、団体交渉の途中で、会社が一方的に賃金を振り込むことがあったため、組合としては、まず、労使間で団体交渉に関するルールを定める必要があると考え、「団体交渉のルールの明確化」を調整事項とするあっせん申請を行いました。
使用者は,「労働組合とは,お互いに信頼関係ができていない。」と主張していましたが,使用者側のあっせん員の働きかけにより,今後は,団体交渉のルールの締結に向けて協力し,話し合うとの意向を示しました。
その結果,「組合と法人は,真摯に話し合い,労使交渉のルールを確立すること。そのルールは,労使の相互信頼を基調とするものとすること。」とするあっせん案を双方が受諾し,解決しました。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す
- 個別労使紛争のあっせん
- 労働争議の調整・あっせん
- 不当労働行為事件の審査の実施状況及び審査期間の目標達成状況
- 個別労使紛争のあっせん事件の取扱状況
- 調整事件の取扱状況
- 労働組合の資格審査
- 不当労働行為事件の審査手続
- 労働委員会委員名簿
- 労働委員会あっせん員候補者名簿
- 宮城県労働相談窓口のご案内
- 労働委員会年報
- 労働争議の調整(調停)
- 労働争議の調整(仲裁)
- 個別労使紛争のあっせん
- 労働委員会による出前講座
- 労働争議の調整
- 公益事業における争議行為の予告通知
- 争議行為の届出
- 申請書・申立書等様式
- 不当労働行為救済申立事件命令一覧
- 「労働委員会労働相談窓口啓発ステッカー」を配布しています
- 不当労働行為の審査
- 労働組合について
- よくあるご質問
- アクセス
- (旧)宮城障害者職業能力開発校トップページ
- 個別労使紛争のあっせん対象とならない紛争
- 労働委員会の概要